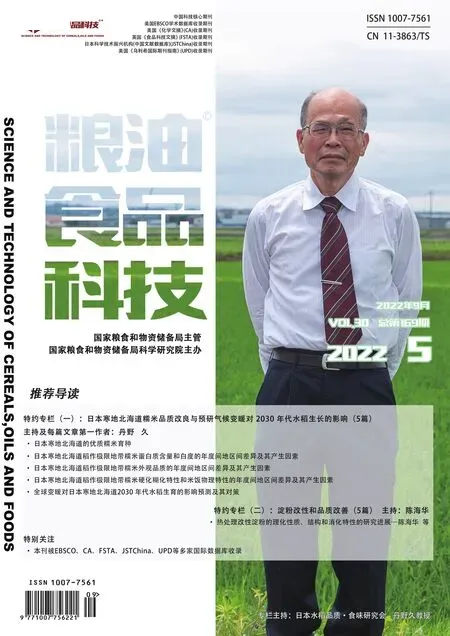|特集のあとがき|
1 .背景
日本水稲品質·食味研究会の丹野久教授が本誌のために論文を執筆するのは、今回が三回目になります。一回目は、2019年9月に開催された「2019日中コメ産業科学技術セミナー」において、私が原稿を依頼し、書いて頂いた論文「日本の寒冷地における良食味米栽培」が、本誌の2019年11月第6号に掲載されました。この時、九州大学の松江勇次教授にも執筆頂いた論文「良食味米生産の栽培理論-登熟期間中における最適な水管理·収穫籾の乾燥温度および玄米水分-」が一緒に、糧科院の孫輝研究員と㈱サタケの河野元信教授が編集したこのセミナーの特集に掲載されました。本誌が創刊以来、初めて外国専門家による論文を掲載し、しかも中国語と日本語のバイリンガルで発表しました。
その後、2019年末に、私は丹野久教授に特集の企画を相談しました。丹野先生は私の要望に応え、北海道米の育種栽培とによる品質向上に関して自身のも含めた日本北海道の研究成果を全面体的系統的に整理し、10篇余りの論文を2~3年に掛けて執筆し、二回の特集に分けて発表する計画を立てました。そして、2020年11月に、本誌2020年第6号で、「日本の寒地、北海道のうるち米における食味と米粒外観品質の向上」の特集として論文5篇(中国語と日本語のバイリンガル)が掲載されました。当時、丹野教授は北海道農産協会に在籍し、本誌のために二回目の論文発表となりました。
三回目は、本号(2022年第5号)に掲載される特集「日本の寒地北海道におけるもち米品質改良および2030年代での水稲生育への温暖化の影響予測」の論文5編で、丹野久教授の執筆計画における後半部分の論文となります。
2 .概要
本特集の論文5編は、すべて丹野久教授が数十年に亘った北海道における良食味米の育種と栽培に関する研究に基づき、他の関連研究成果も含めて系統的に整理し、一年半に掛けて纏められたもので、本誌の発表が最初となります。論文中に示された図表は、著者が関連する大量の原始データ、文献データおよび統計計算結果を基に、客観的に分析し得られたものです。著者は、北海道の研究者による1927~2013年に育成された水稲糯新旧品種の試験データおよび1970~2021年にわたる数十万の試験データを収集整理し、最終的に118点の図表(中では1,000以上のデータに基づいて統計分析した図表は24点)を盛り込んだ日本語6万字余りの連載論文5編に纏め、読者に披露しました。本特集は、日本語の原著と翻訳された中国語の訳文を合せて合計12万字となり、中国の読者に日本の寒いし、寒地における良食味米に関する研究成果を紹介する貴重な場となります。
3 .謝辞
丹野久教授は、2021年1月に本誌の第4期編集委員会副主任委員に委嘱され、2021年2月に本誌の2020年度特別貢献賞に表彰され、本誌の発展にご尽力されました。丹野先生は本誌のために、多くの時間と労力を費やして、数多くの論文を執筆しました。出版作業を通じて、丹野教授の厳格、客観的、きめ細かさ、効率的かつ時間厳守等科学者の精神に感銘を受けました。特に提出された原稿に対し自ら何回も手を加え、完璧さを求める姿に感動しました。
本特集の編集において、本誌の編集委員である河野元信教授に後半4篇の中国語翻訳、あとがきの日本語翻訳、専門的な校正やサポートをして頂き、また殷宏副研究に一番目の論文を中国語に翻訳して頂き、ここで謝意を表します。
最後になりましたが、本誌の発行者の強力なご支援並びに関係者のご協力に対し、心より感謝申し上げます。編集と出版の力不足で不適切な箇所があると思われますが、読者の忌憚のないご意見を頂ければ幸いです。
2022年7月30日、中国北京にて
最終査読:孫 輝 特集依頼と企画:譚洪卓 文章査読:譚洪卓、河野元信
文章翻訳:河野元信、殷 宏 専門校正:河野元信 校正:譚洪卓、尤梦晨、李思源
編集加工:尤梦晨(特集文章)、李思源(特集紹介) 版面設計:郭洪麗(PC5-PC22)
特集供図:丹野 久2022年8月