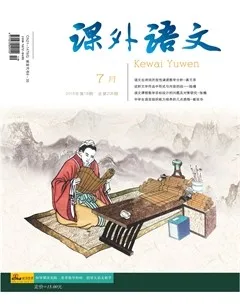句式语法化视角下的日语“Nにする”相关句式群考察
【摘要】本文关注日语“Nにする”成分在句中的作用变化,通过对句式群(N1をN2にする、N1をN2に(して)…、Nにする、Nにしては/も…)的语法化现象考察,剖析群内句式的共性和个性。结果显示它们在句式语义、句法形态、事件识解上有一贯性的语法化倾向。“Nにする”成分伴随句式的主观性程度递增,由作单句谓语向从句成分转变,动词“する”的动作性弱化,“Nにする”形式渐次固定化,结合“は、も”新元素产生新句式。
【关键词】Nにする;句式;语法化;非范畴化;主观性
【中图分类号】G642 【文献标识码】A
一、引言
关于日语句式“N1をN2にする、Nにする、N1をN2に
(して)…、Nにしては/も…”以往研究多围绕个别展开,因此句式间的共性和“Nにする”的句法功能变化少受关注。大堀2004和砂川2006等学者提出将句式扩张也纳入语法化研究视野来考察。本文基于句式语法化视角,从“Nにする”这一共通形式出发,考察上述句式群的语法化现象,描述“Nにする”成分在语义、形态、句法功能上的变化,论证其变化的连贯性和内在机制。
二、语法化和句式扩张
关于语法化现象,过往研究指出其有以下特征:①语义虚化;②非范畴化;③形式固定化;④实词向虚词转变;⑤表达命题到表达情感的主观性变化;⑥语法化过程连续渐变。(砂川2006)另外,大堀2004:31还主张“純然たる脱語彙化だけでなく、構文の発達も文法化の視野に入れるべき”,砂川2006:39也认为有必要结合新生句式思考语法化。
三、“N1をN2にする”句式
该句式表达某动作或作用影响对象N1变化,产生N2的变化结果,“する”作对象变化他动词用,“N2にする”整体作为一个复合谓词起句法作用。如例2、3所示,除“N2に”外,能充当变化结果的还有形容(动)词的连用形,构成“NがNをAする”的对应句式。对“Nに”的句法成分定位,按学者立场大致分为“结果补足语”和“结果副词”两派。
例1:射撃の名手が彼を蜂の巣にした。
例2:歯医者さんで歯を白くしてもらいたいのですが、いくらくらいかかりますか?。
例3:これらの国々の結束の上に立つ彼の立場を困難にした。
例4:それとも君主制を欲する者が天意を口実にしたのか?
例5:英会話学校の広告の多くが女性をターゲットにしたものである。
观察语料,还发现不少像例4、5的句子,与例1—3想通,其皆可转换成对应的“N1がN2になる”句式。语义上,例1—3中“N1”自身发生客观变化,产生“N2”的新属性(形、色、数、程度等)。例4、5理解为“N1”被外界赋予“N2”的新属性,即主观上对“N1”评价判定为“N2”更恰当。从“国統治の口実、英会話サービスのターゲット、研究の重点、サッカープレーの基本”这样的替换表达中可看出该类型“N2”与S①形成一定的关系。在事件识解上,处理“N1”与S间的关系时,S的某侧面属性被定位为“N2”。由于是对对象N1的“思考定位”使得N2归属于S的某属性,本文将该类型语义称为“对象归属评定”。对N1自身属性发生状态变化的类型,则称为“对象状态变化”,以示区别。
关于对象状态变化,认知语言学上一般认为通过空间隐喻的概念映射产生“变化即移动、状态即场所”的理解。笔者认为“对象归属评定”类型根本上也是基于对象位置移动的概念隐喻扩展出来的。用具体物与具体空间的关系来置换理解便是具体物N1在和它的外在空间“S”之间,动作主体判定N1属性“位移”归属到“S”的某个点N2处。“对象状态变化”与“对象归属评定”的另一个区别在于它们的动作性差异。因前者是对象物自身物理状态发生改变,较后者心理上的归属评定,在动作性上显得更明显突出。
另外,例1—5出现在单句中,例6、7则是作为从句成分修饰后续主句,起到样态修饰功能。上述两类型皆可出现在单句和复句中。
例6:ダニエルは右脇を下にして、たちまち深い眠りについた。
例7:身の回りの人々を俳優にして、劇中劇を空想する。
四、“N1をN2に(して)、…”句式
如例8、9所示,前人研究认为“N1をN2に、…”句式在产生上是从“N1をN2にして、…”的“して”形式省略而来,与后置词一脉相联,“して”的有无通常不造成现语义上的差别。“N1をN2に”的语义多表示基准、焦点、理由、目的、时间、空间,作为主句事件实现的附加状况在句中起样态修饰的句法功能。(村木1983:267、田中2010:133)
例8:ぼくは仕事を口実に、家庭を省みなかった。
例9:そんな中国人観光客をターゲットに、各国は中国人観光客の誘致に力を入れている。
句法层面上该句式有“N1をN2に”不可分割,内部语序不可颠倒,“N2”的名词性弱化,甚至出现“を”脱落形成“N1N2に(悪童相手に)”等句法特征。毋庸置疑,这些符合语法化理论提到的形式固定化、非范畴化特点。寺村1983:125还详细论证指出①N1、N2、S之间隐含“N1がSのN2だ”的语义关系;②N2是具有归属性特征的名词;③S(典型用法上)表达动作主体有意图性的行为。张2013得出在表示物体数量、程度、形状、颜色、状态等变化的语义用法以及部分惯用句表达上“して”难以省去。同时也指出在口语对话,新闻标题等需要省略的语体中“して”也可略去不出现。
综上所述,“N1をN2にして、…”句式含有对象归属评定和对象状态变化2个类型,但当其变为“N1をN2に、…”时,2个类型的使用分化倾向显现,即“N1をN2に、…”句式在复句中基本继承了对象归属评定类型。与此相对,对象状态变化类型原则上要求保留“して”而不可省略。
五、“Nにする”句式
该句式表达动作主体从多个候选项中决定和选取N(安达1999:108)。安达1999:108将其归为“Nが(Nを)Nにする”处理,并举例10、11,称因信息上“Nに”成分的重要性更为突出,导致“Nを”成分不出现句中。
例10:店、どこにする?
例11:今日のお昼、ひさしぶりに、お好み焼きにしよう。
笔者对他解释未出现“Nを”成分的论述存疑。观察例10、11,若对“店、お昼”追加助词,显然“店は、お昼は”更自然。这并非是单纯地“は”取代了“を”,而是反映了句式整体语义和事件识解上的不同。如前所述,“N1をN2にする”句式的典型用法是客观描述对象状态变化,而“Nにする”句式的主观评价的一面得到凸显,即“店、お昼”在对话中以主题形式存在,“どこにする”、“お好み焼きにしよう”的发话背景体现了说话人的主观偏好。笔者认为该句式对应的是“(Xは)Nにする”。“Xは”表主题且与句中的“N2に”有关联但不对等。观察例12、13,“キッチンで使う電気施設の様式”“新居を手に入れる方式”的选择和决定并不引起“キッチン、新居”本身的状态变化或归属评定。另外,从“Nにする”与“Nを選ぶ/決める”、“N1はN2になる”对应,但不对应“N1がN2になる”处也可以印证笔者的观点。
例12:今度新築を立てる予定です。キッチンはIHにする予定なのですが、エコキュートにするかどうか迷っています。
○IHを選ぶ ○キッチンはIHになる ×キッチンがIHになる
例13:結婚後の新居は賃貸にしましたか?購入しましたか?
○賃貸を選ぶ ○新居は賃貸になる ×新居が賃貸になる
“Nにする”句式可理解为就主题“Xは”相关的多个事项中的一个点“N”的位移定位。它和“N1をN2にする”句式的接点在于都有对某个事物的操作,不同则是一个以明确的“N1を”形式出现,一个是以“Xは”主题形式或隐含其下的形式存在,对象状态变化是物理层面的操作,对象归属评定和选择决定则是心理层面的操作,不产生“N1を、Xは”自身属性的物理变化。观察例14,它可有对象状态变化和选择决定两种理解。而例15通常很难作对象状态变化解释。造成它们的不同在于主题“N”是否能发生物理状态变化,“仕切り”可以,而“冷奴”通常不会再次发生物理状态变化。另外,在语料中还发现少量“Nに”为名词短语的实例(例16)。这种接续上的限制减少与“Nを”升级为主题“Nは”有关系。
例14:アーチ窓をつくりました。駐車場から上がると庭になります。仕切りはアーチにして、立体感を出しました。 ○仕切りをアーチにして
例15:冷奴は絹ごしにすることもあるけど、もめんがよろしな。 ×冷奴を絹ごしにする
例16:禁煙は明日からにした。(安達1999より)
六、“Nにしては/も、…”句式
如例17、18所示,“Nにしては/も…”句式表示基于某状态,参照社会常识设定的标准,作出意外性的评价(田中2010:49)。要强调的是该“にしては/も”成分的形式固定,我们称其为主观评定句式。
例17:この建物は病院にしては、小さすぎるようだ
例18:書いている学術論文にしても、もちろん教育学が中心ですが、文学、政治学、社会学、歴史学の論文も執筆しています。
例19:この文は中学生が書いたにしては、非常によくできている
例20:それは、理解するのはときに難しいにしても、容易に見て取れる変化だった。。
前述“Nにする”句式出现接续上的限制放宽,但是少数派。如例19、20所示,“にしては/も”前接续谓词的实例已不再是少数,即非范畴化现象明显有加强。高桥2003:274将动词不再发挥原有句法功能(作谓词)或改变原有语义(表动作或变化),形式退化现象称之为“后置词化”。相比“N1をN2にする”和“Nにする”句式,“N1をN2に(して)、…”和“Nにしては/も…”句式中的“して”呈现出了“后置词化”现象,这是其接续从名词扩展到名词短语和小句的原因。“Nにしては/も”句式与表选择决定的“Nにする”句式关联密切,都是针对某主题在心理层面的操作。不同的是“Nにする”句式的动词“する”有“する、した”形式变化,尚可感受到动作性。而“Nにしては/も…”句式无形式变化,“Nにして”表某种状态状况,结合“は/も”产生了新的“假设判定”语义。
七、结语
上述4个句式在语义、句法形式、事件识解上可找到一定的变化倾向。从句式“N1をN2にする”到“N1をN2に(して)…”再到“Nにする”,最后到“Nにして(は/も)、…”,其句式语义和事件识解上由客观表达向主观表达转变的倾向。句法形式上,伴随动词“する”的动作性弱化,前接的“N”成分的句法限制从名词扩展到小句,“Nにする”成分从出现在句末、句中向句首转变,形态上从可变的“Nにする/した/している”向“Nにして”固化,甚至出现“して”消失。导致“Nにする”成分的形式、语义、句法功能变化的原因,笔者认为其与名词成分“N”和动词成分“する”之间的影响力平衡有关,即随着动词影响力的减弱,名词成分不再受动词束缚而趋于自由。对于该设想的合理性,笔者将在今后进一步探索研究。
注释
①寺村1983:123中首先指出了N1、N2、后续主句S(或其中的主语)三者间存在一定的语义关系。
参考文献
[1]村木新次郎.1983.「地図をたよりに、人をたずねる」という言い方[C].渡辺実編.副用語の研究.明治書院.267-292.
[2]寺村秀夫.1983.「付帯状況」表現の成立の条件―「XヲYニ……スル」という文型をめぐって―[J].日本語学2(10):38-46.
[3]安達太郎.1999.『する』の文型と構文[J].広島女子大学国際文化学部紀要(7):105-117.
[4]大堀.2004.文法化の広がりと問題点[J].言語.(4):26-33.
[5]砂川有里子.2006.「言う」を用いた複合辞―文法化の重層性に着目して―[C]/藤田保幸山崎誠.複合辞研究の現在[M].和泉書院.
[6]高橋太郎.2003.動詞九章[M].ひつじ書房.
[7]田中寛.2010.複合辞からみた日本語文法の研究[M].ひつじ書房.
[8]張麗.2013.「XをYにして」における形式動詞「して」の脱落について[C].国立国語研究所.第3回コーパス日本語学ワークショップ予稿集:29-38.
(编辑:龙贤东)