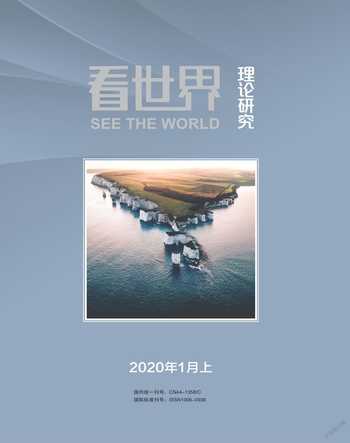「から」と「ので」の比較
摘要:日语中“から”和“ので”都是用來表示原因的接续助词,但它们的使用方法却大有不同。本文围绕 “から”和“ので”的差异展开研究。通过大量的例句从说明事情、报告与指示、“から”的“言いさし”用法和引用功能、以及它们的构文特征这四个方面进行了考察,得出了如下结论。
说明事情时,“から”根据说话人的意志选择说明内容;“ので”则与说话人的意志无关,只强调前后事态间的因果关系。在报告与指示句中,“から”的语气强硬,直接;而“ので”则比较委婉,暧昧。“から”的“言いさし”用法用于传达说话人的态度,引用功能用于传达情报和传闻之类的,这些用法都是“ので”所没有的。在构文特征上,“から”是根据说话人的主观态度得出结论的表现方法;而“ので”则是与说话人的判断无关,通过说明事态回避责任的表现方法。
关键词:から;ので;说话人;事态
一、はじめに
日本語の「から」と「ので」は中国語の「因为」に訳されるが、使い方はかなり違う。
例えば、「雨が降ったから、運動会は延期になった。」と「雨が降ったので、運動会は延期になった。」は、「雨が降った」が運動会が延期になった理由になるが、二つの句が用いられる場合が違う。前者は運動会が延期になった理由の説明に重点を置くため、運動会が延期になった話者の残念な気持ちを表す場合に使われる。それに対し、後者は理由よりも運動会が延期になった事実に重点を置くため、事実の説明によく使われる。このように、両方とも理由を表すにもかかわらず、場面によって「から」と「ので」の使用が違ってくる。
したがって、「から」と「ので」の違いを知ることは日本語学習にとって非常に重要なことである。そこで、本文は「から」と「ので」を比較してみることにした。
二、先行研究
(一)「から」と「ので」をめぐる従来の研究
ここでは、「から」と「ので」をめぐる従来の研究について主要な論点をあげながら再検討を行う。
永野賢(1952)では、「から」が前件を後件として発生した理由を表す言い方であり、「ので」は前件と後件が因果関係にあることが、話し手の主観にかかわらず客観的に事態の関係をそのまま述べる言い方である。つまり、「主観·客観説」という見解を主張している。
また、森田良行(1980)は永野賢(1952)と同じように「主観·客観説」を認めた上で、「から」の前件と後件の関係を話し手の主観的認識に基づいたことと指摘している。
一方、趙順文(1988)は話し手の立場によって、「から」を使う場合は相手が原因を知っている、あるいは相手が原因を知っていると思っている、「ので」を使う場合は相手が原因をよく知らない、あるいは話し手の判断に基づいて使うという見解を提出した。
言語学研究会(1984)は、「から」と「ので」の多くの用例を研究した後、「から」は話し手の積極的な態度や動機を表す場合に多く用いられ、「ので」は原因と結果の事実関係を表現し、話し手の自己主張を和らげる働きがあると説明している。つまり、「から」は話し手の主観が反映されやすい言い方で、「ので」は客観性を含む丁寧な言い方という観点である。
このほかの研究では、田窪行則(1987)は南不二男(1974)の文の階層性の上で、文の焦点の位置によって「から」と「ので」を分けた、「ので」は文の焦点になりにくく、疑問詞があらわれないのに対し、「から」はできると指摘した。
(二)問題点及び本論文の立場
永野賢(1952)の研究以来、「主観·客観説」は基本的に認められている。しかし、実際に「から」が客観的事実に用いられていることや、「ので」に主観性があらわれることはめずらしくない。
(1)a.私は赤点を取ったから経歴に汚点がある。奨学金を受け取れないのだ。
b.この店の看板はとても目立つので、彼が見つけられるに違いない。
c.今日の仕事は全部終わったので、先に帰ってもいいですか。
d.他のお客さんの迷惑になりますので、携帯電話のご使用はご遠慮ください。
このように「ので」を使う場合のaは客観で、bは推量で、cは意志で、dは要求をあらわす。なお、文の焦点によって分ける観点も、「から」でも「ので」でも用いられる場合は説明できない。したがって、単に主観か客観かそれとも文の階層性によって、「から」と「ので」の共通点と相違点はなお十分な説明を見ていないので、より多くの視点を多元的に見直す必要がある。本文では、日常でよく見られる、またはよく使われる例をあげて、「から」と「ので」の違いが何かを検討して分析する。
三、「から」と「ので」の比較
この節では、例を用い、「から」と「ので」を比較する。具体的には、 事情説明、報告と指示、「から」の言いさし表現と引用の機能、構文の特徴という四つの面から考察を行う。
(一)事情説明
「から」と「ので」を比較する時、主観と客観の観点について前件と後件を研究する場合が多い。例えば、「暑いから窓を開けてください。」のような話し手の気持ちを強調するのは、一般的に「から」を使う場合が多く、「ので」を使ったら、暑さに対してみんなが同じように感じている特殊な場合のみ、「暑いので窓を開けていただけないでしょうか。」の形で使う。でも、ある状況には、前件と後件の文は同じような場合もめずらしくない。
(2)a.風邪をひいたので、会社を休んだ。
b.風邪をひいたから、会社を休んだ。
もちろん、この場合のaとbの意味はちょっと違っている。aでは事実関係だけをとりあげ、前件と後件が一つになって、前件の事柄が原因、理由として自然に後件が発生する。bでは休んだことの必然性を確認の意味で話される意味合いが強く、前件と後件が互いに独立し、話し手はわざと理由の部分を特殊に提示している。その場合、「から」は「会社を休んだ」という事実だけを知っているが、その原因を知らない人の推測に使われる。その推測の結果は「用事があった」「事故にあった」などということかもしれないが、「風邪をひいた」はその中の正しい判定だけである。一方、「ので」はほぼ話し手の意図を前に表さず、慎重な態度をとる。また、「雪で新幹線が止まってしまったので、遅刻したものだ。」のように、「ので」で「雪で新幹線が止まる」の偶発的事態は文末の「ものだ」によってさらに説明されることができる。この面、言い切りの「から」はこうした表現ができなく、ただ「(どうして遅刻したかというとそれは)雪で新幹線が止まってしまったから、(それで)遅刻した。 」の感じで遅刻した理由をことさら問い詰められたような場面が想定される。
このほかの「ので」を用いる例は、「彼女を迎えに行かなければならないので、先に帰ってもいいですか。」のように、「なければならない」、「ざるをえないので」や「ことになっているので」などの因果関係の設定した場合は前件が原因理由というより、むしろ後件発生をもたらす背景的な説明である。
つまり、事情説明の面で、「から」は話し手の意識によって、事態の説明を選んだものであるが、「ので」は話し手の意識には関係なく、前件と後件の間の事態の推移を強調している。
(二)報告と指示
ここでは、日常的に頻繁に使用される車內放送を例にあげて、「から」と「ので」で報告と指示のなかの使用傾向を検討する。
(3)JR東日本新型車両搭載の自動放送
a.グリーン車案内:グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますので、ご了承ください。
b.急停車案内:お客様にお願いいたいます。電車は事故防止のため、やむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様は、つり革や手すりにおつかまりください。
c.足元案内(電車とホームの間が空いている駅のみ放送。):電車とホームの間があいているところがありますので、足元にご注意ください。
d.振動注意案内(ポイントを渡るときなどに放送。):この先、電車が揺れますので、ご注意ください。お立ちのお客様は、つり革や、手すりにおつかまりください。
このように、日本の車内放送から見ると、原因理由を表すときに全部「ので」が使われている。それだけでなく、「タバコは健康を損なうことがありますので、吸い過ぎに注意しましょう。」のような多くのスローガン、広告や一般大衆に向けられるアナウンスなど基本的に「ので」を使っている。つまり、不特定な多数の聞き手がある場合は、「から」が直接的で、語気が硬く、勢いに対して、丁寧で客観的な意味を表す「ので」を使って、コミュニケーションを同等に、円滑に進めて緩和している。とはいえ、この情況も絶対的ではない。
(4)a.走行中は危ないですから、ステップに立たないでください。
b.危険ですから、緊急のとき以外は取り出さないでください。
こうした公共の掲示物など、いずれも不特定な多数の聞き手を対象とした伝達であるが、事実の因果関係よりも根拠について述べようとする「から」のほうが、「危ない」とか「危険」などの直接的な警告や注意喚起の面が強い。これに対して、「ので」は事柄の因果関係や事態の推移を伝達すると婉曲的な表現や曖昧な注意になっている。
日本語で、曖昧表現や丁寧さを表すために、口調を柔らかく、意志的表現があっても「ので」を使う場合が多い。
(5)a.この先、道路の幅が狭くなっていますので、徐行してください。
b.花火大会が終わったら大変混雑いたしますので、ご注意ください。
c.外出をしたいと思いますので、留守をよろしくお願いします。
d.定刻に開会いたしたいと存じますので、八時前に会議室に来てください。
なお、強い命令を表す「しろ」や「なさい」などの硬い口調が現れた場合に「から」を使う。
3.3「から」の言いさし表現と引用の機能
日本語のなか、多くの例では、「ので」に比べて、「から」が独特の言いさし表現と引用の機能がある。
その理由は、「から」が結論、結果の先に原因、理由を述べ、補足する用法である。それに対して、「ので」は単に文の順番を変えただけである。
(6)a.彼は用事があったから、欠席した。
b.彼が欠席したのは用事があったからだ。
そのときの「から」は、「AだからB」を置き換えて「BのはAからだ」になる。つまりAはBの説明である。さらに、AとBは相互の独立性が強い。その運用は日本語の会話において、常に結論、結果を省略しながら「から」で終わる「言いさし」の文になる。
(7)a.貧乏だから。(辛いのは当たり前だ)
b.大丈夫だから。(心配するな)
c.時間がないから。(今すぐ出かけよう)
d.いいから。(黙っていろ)
例のような「言いさし」の文は依頼、要請、禁止、勧誘など、何らかの行動を要求するの表現である。その「言いさし」の用法は、話し手の発話態度を表す面が強い。文末の「から」のがあるかどうかにより、意味がが大きく違ってくる。
また、「~といいから」、「~と困るから」、「~といけないから」などの一種の条件句として述部表現を規定、誘導するものもある。これらは「ので」には見られない特徴である。
それから、「から」は引用の機能が見られる。
(8)a.彼の身長が2メートル以上というから二年生の中でも一番高いだ。
b.あそこは風通しの良い場所というから、涼しいですよ。
そこで、前件の「というから」を引用した内容は実質的な意味ではなく、過去に出した情報を再度取り立てるだけである。この場合、ほぼ「~というから~ことになる」の形で引用した情報や伝聞に基づいて伝える。
(9)a.医者の言うことを聞いていないから、こうなるんだ。
b.うちの会社が間もなく休業した。創業1998年というから、20年近く営業してきたことになる。
このような、文末の「ことになる」は「から」で示される引用した内容を合
わせながら説明する。
(四)構文の特徴
ここでは、「から」と「ので」の構文の特徴を検討する。
「から」では、話し手の主観的な態度が表出されて、結論を主張する言い方が顕著である。「ので」は背景引用的な機能によって、自己の判断ではなく、事態に対する責任回避的な意図が提示される言い方が顕著である。
まず、「から」を用いる文の前件と後件の関係に基づいて「から」と「ので」の構文の違いを分析する。
(10)a.私が参加するから、彼は行かないと言ったんですか。
b.泳げたからこそ、助かったのです。
c.今日は月曜日だからか、地下鉄はとても込んでいます。
d.彼は用事があるからではなく、行きたくないだけです。
例から見ると、aのように、「から」には得られた結論は疑問表現でもいいが、「ので」にはこの用法は少ない。bのように、「こそ」などの提示助詞が付いて、理由を強調する時は「から」しか使えない。
また、cとdのように、「から」は間接推量の「からか」と事態修正の「からではなく」を接続することが可能である。「ので」には「のでか」と「のでではなく」の用法がない。
そして、前述の「ので」の機能によって、中立的な並列敘述という構文の特徴を分析する。
(11)友達は中国のある資産家の息子で金に不自由のない男であったけれども、学校が学校なのと年が年なので、生活の程度は私とそう変りもしなかった。したがって一人ぼっちになった私は別に恰好な宿を探す面倒ももたなかったのである。
例のように、「A のと B ので」の構造で「ので」の並列叙述の特徴が見られる。また、伝達情報が複数の場合、中立性が強い「ので」は連続してあらわれることもできる。このとき、「から」に置き換えるには文の表現が不自然になる。
4.おわりに
以上、本文では、従来の先行研究を概観しつつ、例を用い、日本語の「から」と「ので」の違いを考察した。まだ大まかな枠組みを捉えただけで、不十分な点も多いが、次の結論が見えてきた。
まず、一般的な文法の面から見ると、話し手の主張·推測·意志·命令·請求などを表す場合には、「ので」ではなく「から」を使うことになる。
(12)(主張)学生だからよく規律を守らなければならないと思う。
(推測)夕焼けだから、明日はいいお天気になるだろ。
(意志)お客さんが来るから、部屋の掃除をしておこう。
(命令)危ないから、おやめなさい。
(请求)その本が読みたいから、貸してくれませんか。
そして、自然現象·物理現象·社会現象·心理活動または生理現象などを表す場合には、普通は「ので」を使うことになる。
(13)(自然現象)この部屋は南向きなので、日がよく当たる。
(物理現象)引力があるので、リンゴが地に落ちる。
(社会現象)今日はこどもの日なので、学校も工場も休む。
(心理活動)あまり静かなので誰もいないのかと思いました。
(生理現象)一日立っているので腰が痛くなる。
つまり、主観と客観の面で「から」と「ので」がだいたい分かれらるが、分けられない場合もある。その場合、話し手の立場や事態の推移に着眼する必要がある。
参考文献:
[1]永野賢.「から」と「ので」はどう違うか[J].国語と国文学,1952:102-116
[2]南不二男. 現代日本語の構造[M].大修舘書店,1974
[3]田窪行則.統語構造と文脈情報[J].日本語学,1987:5-6
[4]趙順文. 「から」と「ので」ー永野説を改釈する[J].日本語学,1988:89-91
[5]永野賢. 再説―「から」と「ので」はどう違うかー趙順文氏への反批判をふまえて[J].日本語学,1988:7-12
[6] 今尾ゆき子.カラ、ノデ、タメーその選択制限をめぐってー [J].日本語学,1991:10-12
[7]渡辺洋子. 現代助詞論考―「から」と「ので」はどう違うか[J].日本語日本文学,1992:48-53
[8]南不二男. 現代日本語の輪郭[M].大修舘書店,1993
[9]益岗隆志,田窪行则. 基础日本语文法[M].大洋社,1994
[10]姫野伴子.からと文の階層性1―演述型の場合[J].日本語と日本語教育坂田雪子先生古希記念論文集,1995:157-169
[11]姫野伴子.からと文の階層性2―非演述型の場合[J].日本語と日本語教育窪田富男教授退官記念論文集,1995:128-136
[12]于日平.关于“から”的功能转变—表示理由的接续助词用法和表示说话人预期的终助词用法[J].日语学习与研究,2001:5-10
[13]董凤,王战华.“から”与“ので” [J].黑龙江教育学院学报,2006:141-142
[14]杜鹃,王诗荣. “から”与“ので”试论接续助词的句法特征 [J].湖南大外国语学院:社会科学版,2007:74-75
[15]金星.接续助词 “から”和“ので”的区别[J].无锡商业职业技术学院学报,2007:98-99
作者简介:
余达明(1996—),性别:男,湖北仙桃市,汉族,大学本科,研究方向:「から」と「ので」の比较,单位:湖北第二师范学院外国语学院日语系。